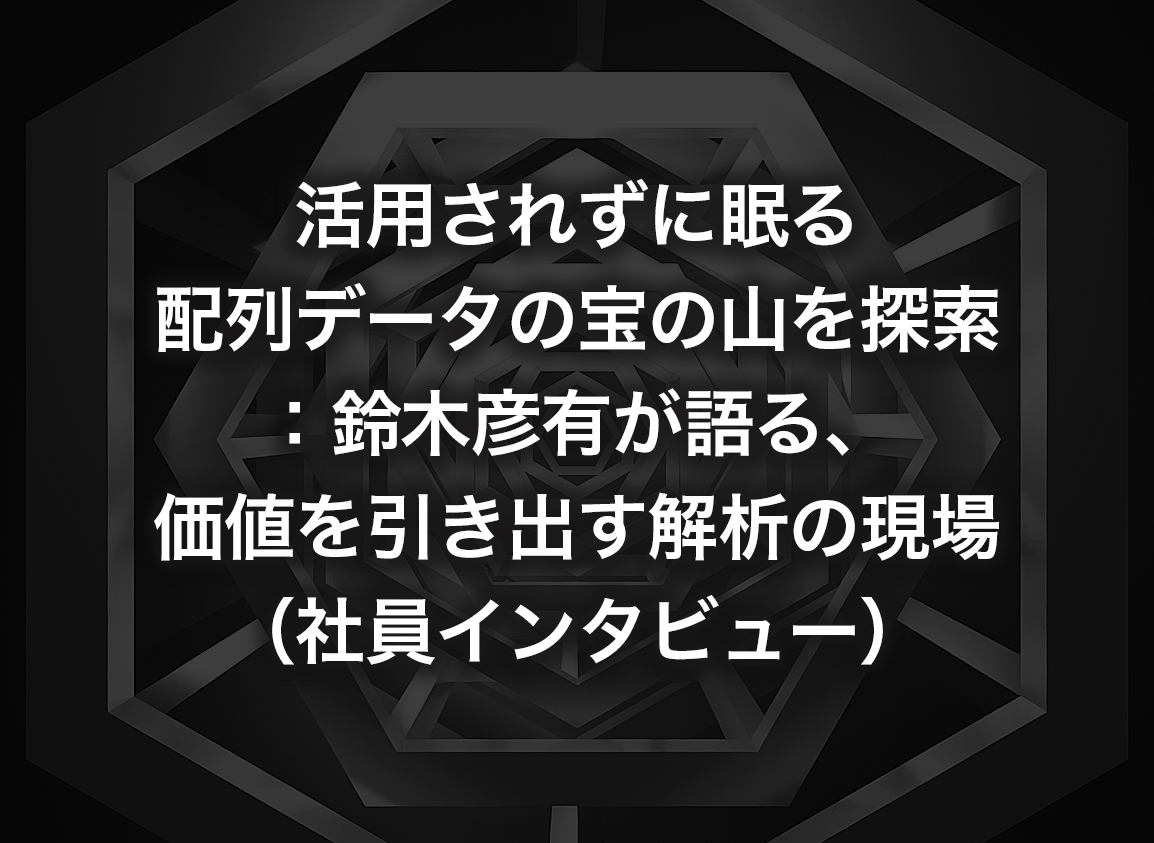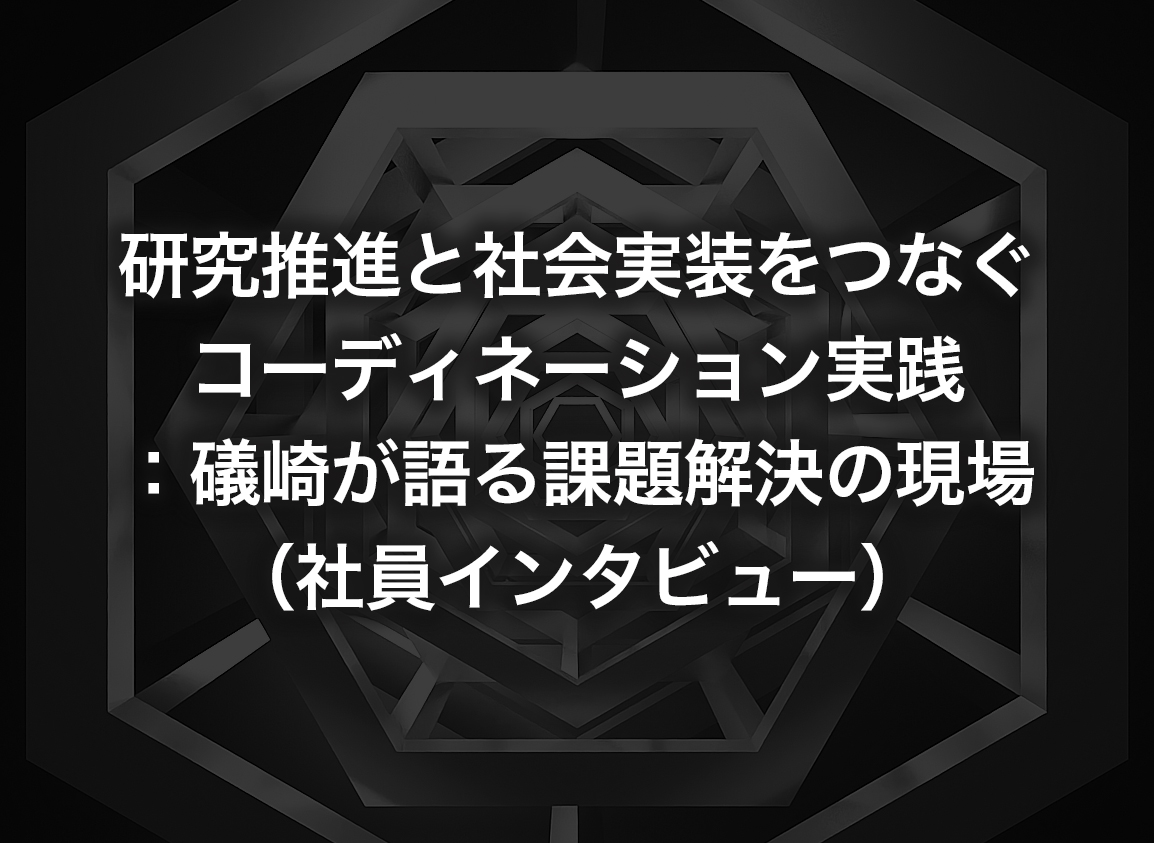食品開発展2025 |CTOプレゼンテーション公開&出展ブースにて頂いたQ&Aまとめ
はじめに
食品事業部の村瀬です。
株式会社digzyme(以下、弊社)は2025年10月15日(水)〜17日(金)に開催された「食品開発展2025」に出展いたしました。会期中は、「出展者・特別プレゼンテーション」に弊社のCTO、中村が登壇し、『差別化できる味・香り・食感の開発に向けたdigzymeにおける産業用酵素の研究開発事例』のタイトルにて、発表を行いました。
その内容を再録し、YOUTUBEで公開いたしましたので、お知らせいたします。
今回は、この度の展示会出展と動画の公開を機に、会期中にいただいたご質問の中から特に多かった内容をピックアップし、回答と合わせてQ&A形式でご紹介いたします。
「出展者・特別プレゼンテーション」の内容を受けて、さらに踏み込んだご質問をくださったお客様や、その他にもdigzymeの産業用酵素や開発プロセスに関してご関心をお寄せいただいた皆様へ向けた内容になっておりますので、宜しければぜひ最後までご覧ください。
Q1.
digzymeがin silico技術で設計した酵素を活用することで、これまで解決が難しかった香りや食感の開発課題に対して、どのような新しいアプローチが可能になりますか?
A1.
弊社では、既存酵素の特性をベースに活性や基質選択性などを向上・調整した新しい酵素を探索・デザインします。そのため、従来では難しかった味・香り成分の比率や、粘りや硬さなどの食感をより細かく制御することが可能になると期待しています。
Q2.
食品素材の味や香り、食感の改良以外には、酵素の働きによってどんな改変ができますか?
A2.
一例として、酵素による食品素材の物性改変が可能です。例えばパンやご飯のデンプンの構造を変化させることにより、時間が経って固くなるのを防いだり、植物性タンパク質を部分分解することにより溶解性を向上させることができます。
既存の酵素では、特定の素材や条件下で十分な改質効果を得られない場合もありますが、弊社ではご希望に合わせて目的の基質や環境条件に適した酵素を設計できるため、これまで難しかった素材に対する物性改変にもアプローチ可能です。
その他にも、酵素を用いることで原料素材から機能性の知られる食品素材に変換・合成することも検討しています。
Q3.
今後、in silicoでの酵素設計で、食品開発の持続可能性や生産効率を向上できる可能性はありますか?
A3.
in silico技術で最適化した酵素は、副生成物を減らしたり、より低温・短時間で反応する設計も可能です。その結果、エネルギーや原料の使用量を抑えつつ、安定した香り・味・食感を提供できるため、持続可能性や効率性の面でも大きなメリットが期待できます。さらに、従来は廃棄されていた副産物や原料も、適切な酵素処理により新たな製品に変換することができるため、食品のアップサイクルにも貢献します。
Q4.
digzyme Moonlightで設計した酵素を効率よく生産するための生産株開発は、今後どのような方向で進める予定ですか?また、将来的にはどんなことが可能になるのでしょうか?
A4.
今回のプレゼンテーションでは詳しく触れませんでしたが、酵素を実用レベルで安定生産するために、生産株の開発を進めています。具体的には、酵素を高効率に発現できる微生物株の選定や、酵素を大量生産するための培養条件の改良などです。将来的には、イノベーティブな酵素を、より高速に事業化していくためのプラットフォームとなる生産株構築システムを確立し、ニーズ対応酵素のデザインから事業化まで一気通貫でお応えできるようになることを目指しています。
終わりに
今回の食品開発展2025では、多くのお客様から具体的かつ本質的なご質問をいただき、酵素デザインへの関心の高まりを改めて実感いたしました。
弊社はこれからも、酵素が持つ可能性を産業界の皆様と共に開拓していきたいと考えています。今回のQ&Aがお役に立ち、皆様の新たな製品開発等のヒントとなれば幸いです。